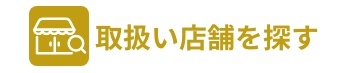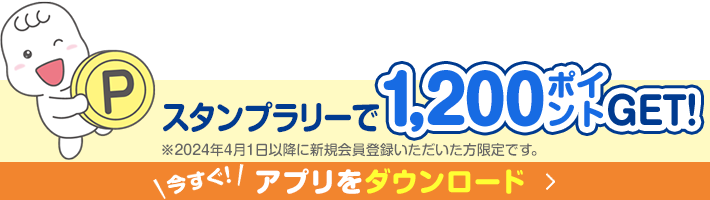無痛分娩の費用はいくら?内訳や相場、メリットを解説

無痛分娩とは本当に「無痛」なのでしょうか?また、費用はいくらくらいかかるのでしょう?痛みが少ない出産方法に興味があっても、知識がなくて一歩踏み出せない人も多いかも知れません。欧米では多数派である無痛分娩について、麻酔科専門医を常勤している井上レディースクリニックの井上裕子先生に監修いただきました。無痛分娩の基本知識と気になるお金について知っておきましょう。
監修者プロフィール

井上裕子先生
井上レディースクリニック 理事長・院長
医学博士。日本産科婦人科学会専門医、日本医師会認定産業医、日本医師会認定健康スポーツ医、母体保護法指定医師。
診療のかたわら、思春期から更年期の様々な女性に対しての講演活動、また、雑誌などに、出演、監修、執筆するなど多方面で活躍。
著書に「産婦人科の診療室から」(小学館)、「元気になるこころとからだ」(池田書店)など。
現在は、NPO法人マザーシップ 代表を兼務。
そもそも無痛分娩とは?
無痛分娩とは、麻酔を使って陣痛の痛みを和らげながら分娩を手助けする方法のことです·。一方で麻酔や手術など医療的な介入を取り入れず行う自然分娩は陣痛の痛みをともないます。無痛分娩といっても痛みの感じ方には個人差が大きいので、全く痛みを感じないわけではなく、やわらげるものと捉えましょう。硬膜外麻酔という局所麻酔を使うことが多く、監修の井上先生のクリニックでもとられている方法です。硬膜外麻酔での無痛分娩は、産婦さんの意識はあるので、おなかが張る感覚や赤ちゃんが産道を通った感覚はわかります。
無痛分娩のメリット
無痛分娩のメリットにはどんなことがあるのでしょう。無痛分娩は欧米では分娩に占める比率が6〜9割と言われています。一方、日本では厚生労働省の「2023年医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、増加傾向にあるとされているものの13.8%とまだ一般的とは言えない状況です。国によって費用や施設、文化が異なるので単純に比較はできませんが、他国が多く取り入れているのはそれなりのメリットがあるからですね。
①陣痛の痛みが和らぐ
無痛分娩は陣痛の痛みが和らげられるので、ママが落ち着いて分娩に臨めます。自然分娩での痛みで血圧が上がったり過呼吸になることで産婦さんの体に負担がかかることがありますが、無痛分娩ではそれを防ぐことができます。
②産後の回復が早い
痛みが少ない無痛分娩では出産時に体力を消耗することが少なく済むため、産後の回復が早い傾向にあります。
③赤ちゃんへの薬の影響はない
麻酔をかけることで赤ちゃんへの影響を心配する人もいますが、無痛分娩で使用されている麻酔薬はもちろん赤ちゃんへの影響が少ないものが使われています。
④帝王切開になってもすぐ対応できる
無痛分娩に限らず自然分娩でも、出産とはいつ何が起こるかわからないもの。どの分娩方法でも分娩中に赤ちゃんや産婦さんの状態が急変して緊急帝王切開を行うことも少なくありませんが、その場合に無痛分娩ではすぐに手術へ切り替えられます。
無痛分娩の安全性とリスク
前述のように無痛分娩で使われる麻酔薬は赤ちゃんへの影響は少ないものですが、無痛分娩で行われる硬膜外麻酔は熟練した麻酔医の技術を必要とされるため、過去に麻酔での事故が起きたことも事実です。日本で無痛分娩が増えない理由のひとつが、麻酔に対する不安が他国より多い文化にあるからとも考えられています。無痛分娩を希望する場合は、麻酔分娩に熟練した麻酔科医・産科医・助産師のいる分娩施設を選ぶことがポイントとなりそうです。
また、リスクとは異なりますが、次の章で解説するように、無痛分娩は自然分娩よりも費用がかかることが一般的です。これは麻酔を使用するための設備費や人件費です。
無痛分娩を選ぶかどうかは、こうしたリスクやデメリットも検討したうえで決めるとよいでしょう。
無痛分娩にかかる費用はいくら?他の出産方法と比較
無痛分娩の費用は、分娩施設や地域、妊婦さんの状態によっても異なりますが、一般的に、その施設で行う自然分娩費用+10〜20万円ほどかかります。
無痛分娩の場合の費用
無痛分娩では自然分娩では使用しない麻酔薬やカテーテル(細い管)を使う費用が追加されます。追加される費用は設備態勢や麻酔医が常駐しているかどうかなどによって産院によってまちまちですが、一般的に自然分娩の費用に約10〜20万円が追加されることが多いようです。
自然分娩の場合の費用
無痛分娩の費用の基準が自然分娩の費用なのであれば、自然分娩にどれくらいかかるか気になりますね。自然分娩の費用も地域や産院の施設によって大きく異なりますが、厚生労働省の2024年度上半期の調査では、正常分娩の出産費用の全国平均は約51.8万円。この数値は年々右肩上がりになっており、特にここ数年は物価や人件費の高騰も影響しているのか2022年度の約48.2万円よりわずか2年で3.6万円も上がっています。
<2024年度上半期調査での正常分娩の各項目の平均額から算出される出産費用>
| 入院料(標準の室料、食事料) | 125,671円 |
| 分娩料 | 306,327円 |
| 新生児管理保育料(赤ちゃんの入院料、検査料) | 51,887円 |
| 検査・薬剤料 | 16,308円 |
| 処置・手当料 | 17,759円 |
| 室料差額(A) | 19,732円 |
| 産科医療補償制度(B) | 11,753円 |
| その他(C) | 40,357円 |
| 妊娠合計負担額 | 589,794円 |
| 出産費用(妊娠合計負担額から(A) ~ (C)を引いた額) | 517,952円 |
|---|
※出典:『出産費用の状況等について』2024年11月21日 厚生労働省
自然分娩や無痛分娩は公的保険が適用されないので、基本的には全て自費になります。ただし、これらを全額負担しなければならないわけではなく、出産育児一時金という強い味方がありますのでご安心を!健康保険や国民健康保険に加入していれば、出産育児一時金として子ども一人につき50万円(妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は48.8万円)が支給されます。申請方法は勤務先等で加入している保険組合や、分娩する産院の窓口で確認してみましょう。
自然分娩の費用は入院する部屋タイプで大きく異なる!
自然分娩の費用は産院によって異なりますが、同じ産院でも費用に幅があることがほとんど。それを左右しているのは入院する部屋のタイプです。通常の病気で入院するときも同じですが、大部屋より個室の方が割高になりますし、部屋にシャワーやトイレが付いているかによっても変わってきます。
帝王切開の場合の費用
帝王切開にかかる費用は手術費が公的保険適用となるため、少し複雑になります。
前述の出産費用の内訳のように、正常分娩の場合の分娩料は約30万円で、公的保険が使えないため全て自費になりますが、帝王切開は手術という扱いのため、公的保険の適用となるのです。そして公的保険適用の場合は、診療報酬の対象になるためどこの医療施設でも同じ金額で、予定帝王切開の場合は201,400円、緊急帝王切開の場合は222,000円*で、このうちの3割が自己負担となるので、約6万円ということになります。
また、帝王切開が保障の対象になっている民間の生命保険会社の医療保険に入っている場合も、保険会社から給付金を受け取れる場合があります。ただし、妊娠前に加入していたなど条件があります。
しかし、入院期間は一般的に自然分娩が5〜6日に対し、帝王切開は7〜8日前後と長くなり、その分ベッド代や食事代などの入院費は高くつきます。そのため合計では、自然分娩よりも帝王切開の方が5〜15万円程度高くなる産院の方が多い傾向にあるようです。つまり、自然分娩の平均が51.8万円に対し、帝王切開の場合は約60〜70万円程度になるケースが多いようです。
*出典:「産婦人科社会保険診療報酬点数早見表」日本産婦人科医会(令和4年4月)
出産にかかるその他追加費用
出産予定日がわかっていても、計画的な予定帝王切開を除き、実際に赤ちゃんがいつ生まれてくるかは誰にもわかりません。分娩する施設では基本的な診療時間が決まっているため、時間外の分娩になった場合には追加費用がかかります。また出産時には何が起きるかわからないものなので、想定外の事態が起きた場合には追加費用がかかる場合があります。出産後に「こんなにかかるとは思わなかった!?」ということがないように、事前に産院に確認しておくと良いでしょう。
①時間外加算・深夜加算
分娩する施設の診療時間外や深夜、または予定外の緊急な時間外の分娩は割増料金となることがほとんどです。割増料金の金額は、産院によって異なりますが、おおよそ2〜4万円が多いようです。
自分が出産する産院についてもホームページや入院前にもらうパンフレットの記載を確認しておきましょう。
②陣痛促進剤の費用
陣痛がなかなか進まない場合、陣痛促進剤を使用することがあります。その際、追加で費用が発生する場合があります。金額は分娩の状態などによって異なります。
③鉗子分娩・吸引分娩の費用
鉗子(かんし)分娩や吸引分娩は、帝王切開と同様に異常分娩と位置づけられており、公的医療保険の適用対象になっています。診療報酬点数表による分娩費用の金額は、吸引分娩は25,500円、鉗子分娩は低位(出口)鉗子の場合は27,000円、中位鉗子 の場合は47,600円*。それぞれ自己負担は3割となるので、吸引分娩は7,650円、低位(出口)鉗子分娩は8,100円、中位鉗子分娩は14,280円ということになります。詳細は分娩する産院に問い合わせてみましょう。
*出典:「産婦人科社会保険診療報酬点数早見表」日本産婦人科医会(令和4年4月)
無痛分娩の費用に関するよくある質問
ここまでで見てきたように、分娩にはさまざまな方法があるため、費用も複雑でわかりにくいかもしれません。無痛分娩についてよくある質問についてお答えします。
無痛分娩の費用は保険が適用されますか?
前述のように、無痛分娩には公的医療保険は適用されません。出産はケガや病気とは見なされないためです。帝王切開や鉗子分娩、吸引分娩などは「異常分娩」と位置づけられ、出産時に赤ちゃんやママの生命が危険にさらされることから守るための手術や処置が施されるため、保険が適用されますが、無痛分娩はこれには該当しないということです。
東京都では、2025年10月1日より無痛分娩に係る医療行為に要した費用対して最大10万円の助成をすることになりました。他の自治体でも同様の制度がひろがるといいですね。
無痛分娩の費用が産院によって異なるのはなぜ?
一つには無痛分娩に限らず、自然分娩でも出産にかかる費用の地域差が大きいことがあります。2024年度上半期の正常分娩の都道府県別平均出産費用では、最も高かった東京都が646,203円、最も低かった熊本県が402,255円とその差は24万円以上※。
また、同じ地域でも費用が異なるのは、無痛分娩で重要な役割を担う麻酔医が常勤しているかどうかにもよります。麻酔医が常勤している産院の方が安心して臨むことができますが、その分人件費の点では高めになっていることが多いようです。
※出典:『出産費用の状況等について』2024年11月21日 厚生労働省
無痛分娩にも出産育児一時金は適用されますか?
はい。出産育児一時金は、職場の健康保険や国民健康保険に加入している人であれば、どんな出産方法の人でも受け取ることができる給付金です。子ども一人当たりに50万円支給されるので(妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は48.8万円)必ず手続きしましょう。
出産育児一時金は医療保険組合などから直接産院に支払ってもらえる直接支払制度があります。直接支払制度を導入している産院で出産すれば、退院時には出産育児一時金との差額だけを支払えば良いことになります。産院からの請求額が出産育児一時金よりも下回る場合には、後日申請書類を揃えて請求すれば差額を受け取ることができます。
無痛分娩は聞いたことがあっても、まだ日本では一般的とは言えないので、どうするか悩んでいる人もいるかもしれません。無痛分娩を選択する場合、多くの施設では陣痛発来前に入院する計画分娩が多いです。自分が痛みに弱いと言う自覚があり、痛みに対する恐れがある人は、いちど主治医の先生に相談してみると良いかもしれません。かかる費用やメリット・デメリットを理解した上で、自分が納得できる分娩方法を選べると良いですね。
取材協力/井上レディースクリニック院長 井上裕子先生
はじめてのおむつ交換もあんしんの「おしりガイド」をご存じですか?

ムーニーは、赤ちゃんのおしりを置く場所がひと目で確認できる「おしりガイド」で、ママもパパも誰でも正しく簡単におむつ替えができます。
release : 2025.04.15
- お気に入り機能はブラウザのcookieを使用しています。ご利用の際はcookieを有効にしてください。
また、iPhone、iPadのSafariにおいては「プライベートブラウズ」 機能をオフにしていただく必要があります - cookieをクリアすると、登録したお気に入りもクリアされます。