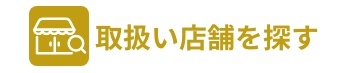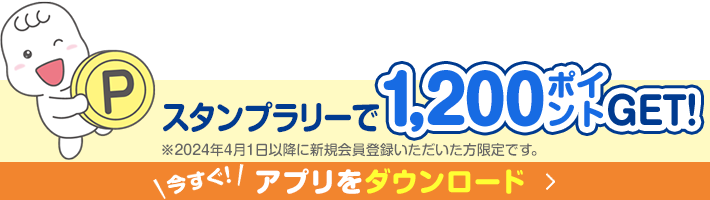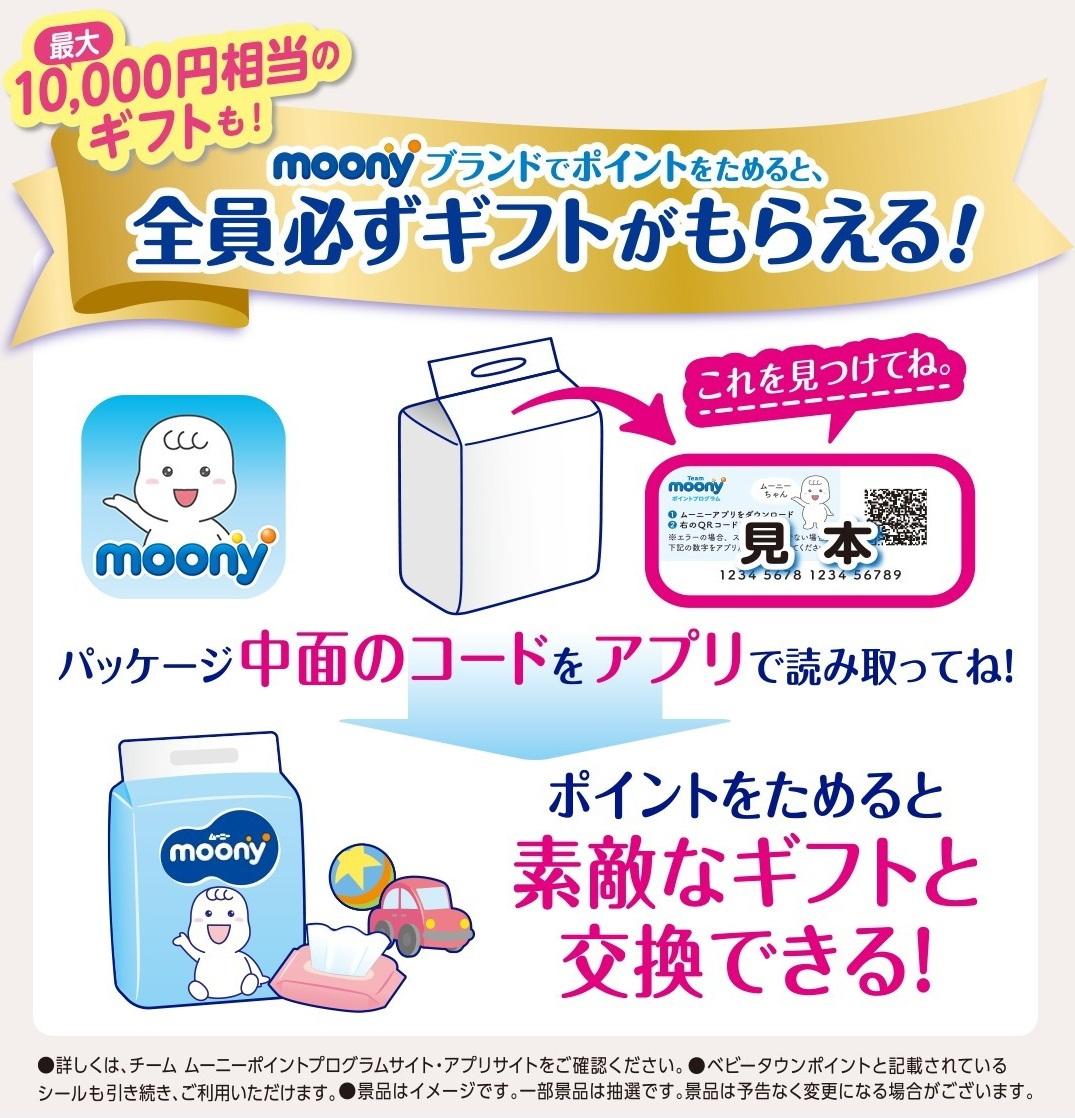赤ちゃんに生活リズムはなぜ必要?睡眠はなぜ大切?

赤ちゃんの1日の生活のリズムは少しずつ変化して大人のリズムに近づいていきます。同様に、食事や睡眠、遊びの時間や内容も変わっていきます。ママやパパ自身の日頃の過ごし方やちょっとした働きかけで、規則正しい生活の習慣を覚えさせてあげましょう。
監修者プロフィール

池田裕一先生
昭和大学藤が丘病院小児科診療科長
1995年昭和大学医学部卒業後、同大学藤が丘病院小児科に入局。
1998年~神奈川県立こども医療センター感染免疫腎内科、昭和大学医学部小児科講師、カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF ,Children Hospital Oakland,CA, USA)客員研究員等を経て、現在は昭和大学医学部小児科学講座教授、昭和大学藤が丘病院小児科診療科長、昭和大学横浜市北部病院こどもセンター長(小児内科診療科長兼務)。
また、「尿トラブル外来」を担当、HPこどものおねしょとおもらし総合相談室「おしっこトラブルどっとこむ」や講演、執筆、TV出演(NHK)等、子どもの排尿の問題のほか、こどものすいみん総合相談室「すいみんトラブルどっとこむ」で子どもの睡眠問題に取り組んでいます。
生活のリズムって?
私たちはあたりまえのように「生活のリズム」をとっているように見えますが、それは本来生まれ持ったものなのでしょうか?まずは生活のリズムの基本を知っておきましょう。
大人のリズムが影響します
人の体は、昼間は活動し(遊び)、食事をとり、夜間は静かに眠るようになっています。これが生活のリズムの基本です。
生まれて間もない頃の赤ちゃんは、昼も夜もなくおっぱいやミルクを飲んだり眠ったりですが、親が生活のリズムの基本を理解して赤ちゃんと接しているうちに、次第に昼と夜のリズムにそって眠ったり飲んだりするようになります。生活のリズムには食事と睡眠の時間が深く関係しています。
親が夜更かしだったり食事の時間が不規則だと、赤ちゃんも健全な生活リズムがつきにくくなってしまうことを知っておきましょう。

食事のリズム
食事の時間を決めることは、大人にとっても生活時間を区切るちょうどいいタイミングになりますね。赤ちゃんも同じように食事、つまり離乳食の時間を固定することで、生活のリズムがつけやすくなります。
授乳は赤ちゃんなりにおおよその間隔が決まってくる
生後1ヶ月頃までの授乳回数は1日8~14回と言われます。8回と14回の赤ちゃんでは、当然、1回に飲む量も間隔も違い個人差があります。時間を決めつけないで、赤ちゃんが飲みたがっているときに授乳をしましょう。3ヶ月頃になると個々の赤ちゃんで飲む時間が決まってきます。この頃には赤ちゃんも飲み方が上手になり、短時間でたくさん飲めるようになります。もう栄養は十分なのに、それでもまだまだ甘えて「遊び飲み」する子もいます。1回の授乳時間は赤ちゃんの様子を見て。「もう十分飲んだな」と思ったら、ゲップをさせて「おしまいよ」と合図しましょう。
離乳食がスタートしたら
母乳やミルクと並行して生後5~6ヶ月頃(離乳初期)から1日1回の離乳食がスタート。7~8ヶ月頃(離乳中期)から1日2回、9~11ヶ月頃(離乳後期)には3回になります。主な栄養源が、母乳やミルクから、離乳食へと進むにつれ、授乳の回数も減っていきます。離乳食の時間は固定しましょう。食事を中心とした1日のリズムがつけやすくなります。食事の前にはぬれタオルなどで手を拭き、「いただきます」、食後には口元や手をぬぐって、「ごちそうさま」と声をかけるようにしましょう。赤ちゃんが、「今からごはんが始まるんだ」とか「これでごはんが終わったんだ」と、生活シーンの区切りを理解しやすくなります。

睡眠のリズム
赤ちゃんにとって睡眠は成長に関わるとても大切なこと。ただ眠るだけでなく、「良い眠り」をすることが大事で、そのためには睡眠時間、睡眠の質、睡眠リズムのすべてが整っている必要があります。これらが整うことで、生活のリズムも規則正しくなり、健やかな成長につながります。
睡眠はなぜ大事?
睡眠の段階は大きく分けてレム睡眠とノンレム睡眠の2つがあります。レム睡眠は睡眠中でも目がクリクリと動いて脳が活動している浅い眠りの状態、ノンレム睡眠は目の動きがなく脳が休息している深い眠りの状態です。人は眠っているときに、レム睡眠とノンレム睡眠のセットを一晩の間に繰り返していますが、それぞれに大切な役割をもっています。
レム睡眠中には脳の神経回路が生成されており、子どもは大人よりもレム睡眠の割合が多い特徴があります。
また、寝ついてから最初に訪れるノンレム睡眠中には成長ホルモンがに分泌されていて、子どもの体の組織と脳の成長を促しています。
また、睡眠のリズムが崩れることは、幼児になってからのおねしょの原因になることもあります。
だから赤ちゃんや子どもにとって睡眠は成長や発達にとても重要なことで、睡眠時間をしっかり確保することが大切なのです。
健康な睡眠とは?
早寝早起き
健康な睡眠の基本は早寝早起き。規則正しい生活リズムをつけるだけでなく、睡眠の質を高めるために大切なことです。
寝つきがよいこと
健康な子どもは布団に入ってから眠りに落ちるまでの時間が短く寝つきがよいです。2~5歳では平均13分。成人(20~50歳)の平均は32分と言われているので、子どもたちがいかに早く寝つくかがわかりますね。
十分な睡眠時間
新生児の赤ちゃんの頃は、寝たり授乳をしたりの繰り返しですが、ほとんどを眠って過ごすため睡眠時間が1日で16~18時間。成長にともなって少しずつ起きている時間が長くなっていき、生後6ヶ月頃~2歳で13時間。徐々に昼間に起きている時間が長くなって、夜に眠るというリズムになっていきます。この時期に早寝早起きと、しっかり睡眠時間をとる習慣をつけましょう。遅くとも夜8時までにはお布団に入ることを目標としたいです。
眠りが深い
もっとも深い睡眠の割合は、2~5歳で平均15〜25%。成人の50歳では平均2%ですから、いかに子どもが深い眠りが多いかわかります。
睡眠のリズムをつけるには
睡眠の質を高めるためにできることを見ていきましょう。
太陽の光を浴びる日中の活動を増やしましょう
良い眠りには、外遊びや散歩など、朝日や日光を浴びるようにすることが大切です。
朝起きたときは、最低10分程度、日差しが顔や身体にあたるように窓際で過ごさせてあげてください。

毎朝同じ時間に起こしましょう
前日に遅く寝てしまった場合でも、翌朝はいつもと同じ時間に起こしましょう。睡眠時間を確保しようと朝遅く起こすと、その分夜の眠気が訪れるのも遅くなるので、睡眠のリズムが不安定になっていきます。
日中子どもが眠そうになったら、外に連れ出したり、子どもの興味のある作業を一緒に行ったりして、夜まで寝ないようにがんばってください。

朝食を食べましょう
体内時計を適切に保つためには、決まった時間に食事を取ることが大切です。離乳食が3回食になった以降、特に朝食は体内時計の安定と活性化に重要な役割を担っていると言われています*。眠っていた時に下がっていた深部体温を上げる役割もはたすので、少しでもエネルギーになるものを摂取させるようにしましょう。
*この仕組みについては諸説あり、不明な点も多いです。
夕食は早く、お風呂は熱すぎないように
良い睡眠のためにも就寝3時間前までには夕食を終わらせたいです。また、夕食後のおやつは成長ホルモンの分泌を悪化させるので食べない習慣をつくりましょう。
お風呂はぬるめのお湯で、就寝の2時間前までに入って、体温が徐々に下がった状態で布団に入るように心がけてください。
就寝前の同じ行動(ルーチンワーク)を作りましょう
人は同じ行動をとると、気分が安定して心がやすらぎます。そのためには、就寝前には平日も週末も同じ行動(ルーチンワーク)をしましょう。
例えば、幼児には夕食後「お風呂」「歯磨き」「トイレ」「読み聞かせ」「お休みの歌」などを毎日繰り返します。具体的な就寝の準備をすることで、少しずつ「そろそろ寝るんだな~」と心の準備を促して、日中の起きている状態から眠りの状態に切り替わっていくようになります。
寝る1時間前にはテレビ、ネット動画、スマホを止めましょう
テレビや動画は脳の視覚中枢を刺激し、寝ついてもしばらく活動を止めません。また、スマホやPCなどのブルーライトは同じく視覚野や前頭葉の活動を活性化してしまいます。
動画、スマホは寝る1時間前にはやめて、寝室には持ち込まないようにしましょう。
寝かしつけ便利グッズ
赤ちゃんをやさしく眠りに導く便利なグッズをご紹介します。
ベッドメリー
オルゴールのやわらかい音色と、くるくる回るモビールに夢中になっているうちに、眠りにつきます。
胎内音オルゴール
ママの胎内の音を鳴らすオルゴール。なじみ深い音にリラックスします。
ベビーモニター
赤ちゃんが寝たと思ってママやパパが寝室を出た後に、赤ちゃんが寝つけていなくて泣いてしまっていることもあります。寝室とリビングが離れている場合など、寝室にカメラを取り付け、離れた場所にいてもモニターで赤ちゃんの様子を確認できます。双方向タイプなら、ママやパパの声を聞かせられます。ただしスマホ同様、赤ちゃんがおもしろがって眠れなくなってしまうこともあるので、使い方は工夫しましょう。
ベビーラック
お昼寝用に。リビングや食卓でも使えます。体重でシートがたわみ、ほどよい揺れが眠りを誘います。
監修/昭和大学藤が丘病院小児科診療科長 池田裕一先生
release : 2022.01.26
- お気に入り機能はブラウザのcookieを使用しています。ご利用の際はcookieを有効にしてください。
また、iPhone、iPadのSafariにおいては「プライベートブラウズ」 機能をオフにしていただく必要があります - cookieをクリアすると、登録したお気に入りもクリアされます。