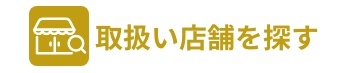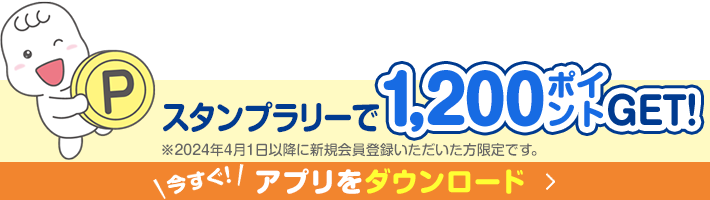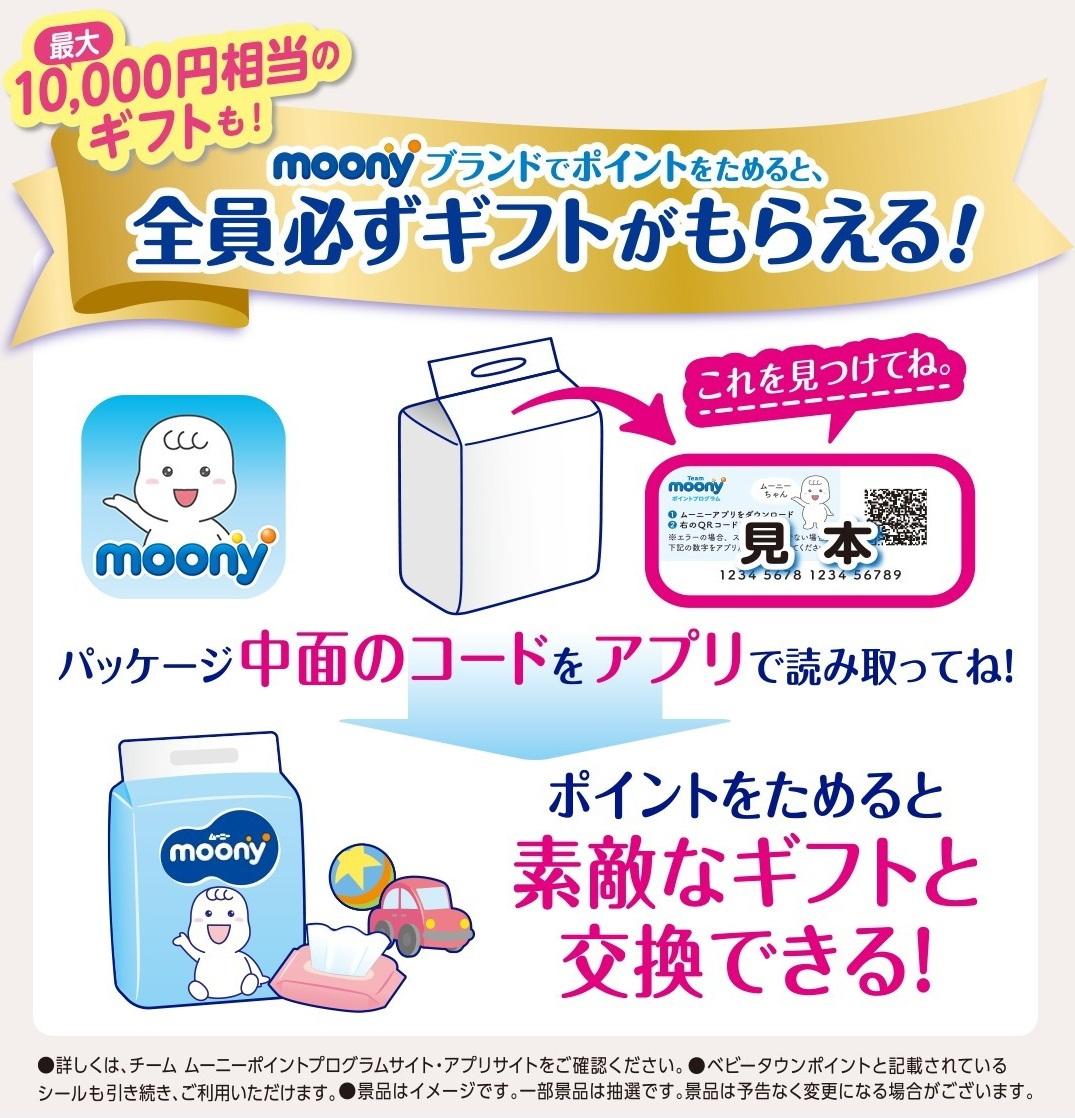【医師監修】新生児のくしゃみの原因と対処法は?受診の目安を解説

新生児の赤ちゃんがよくくしゃみをしていると、誰でも心配になるもの。しかし、多くの場合は正常な発達や環境の変化による自然な反応で、必ずしも病気の兆候ではありません。この記事では、新生児のくしゃみの主な原因をわかりやすく解説し、風邪やアレルギー性鼻炎などが疑われる場合の注意点も紹介します。家庭でできる環境対策や、すぐに受診すべき緊急サインもまとめているので、日々のお子さんの観察やお世話に役立ててください。
監修者プロフィール

今西洋介先生
一般社団法人チャイルドリテラシー協会代表理事
小児科医・新生児科医。日本小児科学会専門医/日本周産期・新生児医学会新生児専門医。医学博士(公衆衛生学)。一般社団法人チャイルドリテラシー協会代表理事。小児公衆衛生学者。富山大学医学部卒業後、都市部や地方のNICU(新生児集中治療室)で新生児医療に従事。「ふらいと先生」の名で、小児医療や育児に関する啓発を行い、社会問題解決に取り組む。現在は米国在住。3姉妹の父。 主な著書に『新生児科医・小児科医ふらいと先生の子育て「これってほんと?」答えます』(西東社、監修)、『小児科医「ふらいと先生」が教える みんなで守る子ども性被害』(集英社インターナショナル)ほか多数。
新生児がくしゃみをする理由
新生児のくしゃみには、主に以下のような原因があります。
- 体に備わる反射によるもの
- 鼻の粘膜が敏感で刺激を受けやすいため
- 鼻毛が未発達で、ほこりやウイルスをキャッチできないため
それぞれ詳しくみていきましょう。
反射によるもの
赤ちゃんに限らず、人間は「反射」と呼ばれる体を守るための生理反応を持っています。くしゃみもそのひとつです。
新生児は、刺激を受けると反射的に体を動かしたり声を上げたりします。くしゃみの場合も、ほこり、匂い、急な空気の変化など外部からの異物や刺激を感知した際に自動的に現れる防御反応の一種です。
こうしたくしゃみは一時的なもので、赤ちゃん自身がひどく苦しそうにしていなければ、心配しすぎる必要はありません。くしゃみそのものは生涯を通して大切な防御機能として残ります。
鼻の粘膜が敏感なため
新生児の鼻の粘膜はとても敏感で、大人よりも刺激を受けやすいという特徴があります。室内のほこり、空気の乾燥や冷暖房による温度・湿度の変化、わずかなにおいでもすぐに反応し、くしゃみが出やすくなります。
これは、まだ鼻腔や粘膜の発達が未熟で、小さな刺激にも過敏に反応するからです。赤ちゃんによっては、お風呂に入る時や布団をかけた時など、環境が変化するごとにくしゃみをすることがあります。
特に空気が乾燥した冬場や、換気をして空気を入れ替えた時に、頻繁にくしゃみをするケースが目立つことがあるでしょう。しかし、これも新生児の反応として正常な範囲なので、それほど心配は必要ありません。
鼻毛が未発達なため
新生児の鼻には、ほとんど鼻毛が生えていません。鼻毛は、本来なら空気中のほこりやウイルス、花粉などの異物が鼻から体内に侵入するのを防ぐフィルターの役割を果たします。
しかし、赤ちゃんはこのフィルター機能がまだ十分に発達していないため、鼻から入る異物やウイルスをうまくキャッチできません。その代わり、こうした異物を体内に入れず外へ排出する方法として、くしゃみが活躍します。
くしゃみは、生理的反射として鼻にたまった異物や微粒子を外に押し出そうとする動きであり、鼻毛が未発達な新生児にとってごく自然な現象です。頻繁なくしゃみも、病気でなければ問題はありません。鼻毛の発達は成長とともに進んでいきます。
新生児のくしゃみで疑うべき病気
くしゃみが続いて止まらない場合や、他の症状が重なる場合は、次のような病気の可能性もあります。
- 風邪(発熱・咳・鼻水・ぐったり)
- アレルギー性鼻炎(透明な鼻水・鼻づまり・目のかゆみ)
それぞれ詳しく説明します。
風邪
新生児がくしゃみを頻繁にし、さらに発熱や鼻水、咳といった症状を併発している場合は、「風邪」が疑われます。
生まれたばかりの赤ちゃんは、免疫機能がまだ十分に発達していません。ちょっとしたウイルスにも感染しやすい状態です。特に新生児期から乳児期にかけては、複数回風邪をひくのも珍しいことではありません。
風邪の症状は、最初は透明な鼻水から始まり、徐々に鼻づまりや黄色い鼻水に変化していくのが特徴です。さらに咳や発熱が加わると、重症化することもあります。症状が数日続いて改善が見られない場合や、38℃以上の発熱が見られる場合は、自己判断せず早めに小児科を受診してください。呼吸が苦しそう、ミルクをあまり飲まない、哺乳量が明らかに減っているなどの様子が見られる場合も、できるだけ早く受診をしましょう。少しでも異変を感じたら迷わず専門家の判断を仰ぐことが大切です。
生後3ヶ月未満の赤ちゃんは、母親より移行抗体があり免疫が保たれています。そのためいわゆる「風邪」は引きにくいとされています。3ヶ月未満の発熱は細菌感染の可能性があるのため、早めに医療機関を受信しましょう。

ここでは、先輩ママからの体験談をご紹介します。
![]()
神奈川県:たばじゅん
微熱で元気だったので、しばらく様子を見て病院には連れて行きませんでした。でもだんだん鼻水が出たり咳き込んだり、吐き戻したり症状が悪化してしまい、病院に連れて行こうと思ったときには診察時間外。
結局次の日の朝に病院に行きました。ちょっとおかしいなっと思ったら、まずは病院に行って診てもらったほうが自分も落ち着いて対応できるし、子どもにも辛い思いをさせずにすんだなぁ、と反省しました。
大阪府:匿名希望(。・ω・。)
生後2ヶ月では風邪はひかないと聞いていたのに、鼻づまりや咳があり、受診すべきか迷いました。機嫌も良かったので、大丈夫かなと思いつつも受診し、先生に「心配しなくても大丈夫」と言っていただき、非常に安心しました。初めての子どもが苦しそうにしていると焦ってしまうので、親が安心するためにも念のため受診はアリなのかなと思いました。
![]()
新生児鼻炎
新生児のアレルギー性鼻炎は極めて稀です。鼻水、鼻づまり、くしゃみといったアレルギー性鼻炎に似た症状が新生児に見られることはよくあります。これらは「新生児鼻炎」などと呼ばれ、多くはアレルギー以外の原因によるものです。タバコの煙、ホコリ、ペットの毛、香水などの刺激物が鼻の粘膜を刺激し、鼻水や鼻づまりを引き起こすことがあります。これはアレルギー反応とは異なる、非アレルギー性の反応です。
くしゃみや鼻水が長期間にわたって続く場合や、授乳や睡眠の妨げになるほど鼻づまりがひどい場合は、小児科や耳鼻科で相談し、必要に応じて原因物質の特定や適切な治療を受けるようにしましょう。
新生児のくしゃみがひどい時の対処法
くしゃみが多い時は、以下のような家庭での対処法が基本です。
- 部屋の掃除や拭き掃除、こまめな換気でホコリやダニの除去を徹底する
- 室内の湿度(50~60%程度)を適度に保つ
具体的に説明します。
部屋を清潔に保つ
新生児のくしゃみ対策には、室内を清潔に保つことが何より大切です。ポイントは、くしゃみの主な原因となるハウスダストやダニ、ペットの毛を減らすこと。毎日少なくとも1回は、赤ちゃんの寝具やカーペット、ぬいぐるみの周辺などを念入りに掃除機で清掃しましょう。
さらに、週に2~3回の床や家具の拭き掃除も効果的。濡れ雑巾や市販のウェットシート、クリーナーシートを使って、細かいホコリやダニをしっかり除去してください。
他に、部屋の換気をこまめに行い、空気の入れ替えを徹底することも意識しましょう。エアコンや加湿器、空気清浄機のフィルターも、月1~2回を目安に掃除することが推奨されます。ダニやカビの繁殖を防いで、赤ちゃんが快適に過ごせる環境を整えましょう。
適切な湿度を保つ
新生児は鼻の粘膜がとても敏感なので、部屋の乾燥もくしゃみや鼻詰まりの原因となりやすい要素です。
理想的な室内の湿度は、50~60%。これを保つことを心がけましょう。加湿器を使用する場合は内部のタンクやフィルターを週1回以上清掃し、水は毎日新しいものに交換を。加湿器がない場合は、濡れタオルや洗濯物を室内に干す方法でも湿度を上げるのに効果があります。
もうひとつ大切なのは、湿度計を使って細かく湿度をチェックすることです。乾燥がひどい日には、少量の水分補給も意識してください。ただし、湿度が高くなりすぎると結露やカビの発生原因になることもあります。加湿しすぎにも注意し、適度に換気を行うことにも注意を払いましょう。
受診の目安 すぐに病院に行くべき症状
赤ちゃんがくしゃみをするだけでなく、次のような症状が見られた場合は、すぐに医療機関を受診してください。特に高熱・呼吸困難・哺乳困難などは重篤な症状です。夜間や休日でも迷わず受診しましょう。
□38℃以上の発熱がある
□顔色が青白い、唇が紫色になっている
□呼吸が苦しそう、ぜーぜー・ヒューヒューなどの呼吸音が聞こえる
□母乳やミルクをほとんど飲まない、哺乳力が極端に低下している
□激しい咳や長く続く咳が見られる
□極端に機嫌が悪い、泣きやまない、ぐったりしている
□尿や便の回数が極端に少ない、おむつがあまり濡れない
よくある質問
新生児のくしゃみの頻度はどのくらい?
新生児のくしゃみは、1日に数回程度なら正常範囲です。これは鼻の粘膜が敏感だったり、環境のホコリや空気の変化などに反応したりするため。特に異常なことではなく、心配いりません。一時的なくしゃみなら様子を見て大丈夫です。
新生児が寒いと感じている時のサインは?
お腹や背中、うなじなどを触ってみて、ひんやりと冷たければ寒いと感じているサインです。また、顔色が悪かったり、いつもより元気がなく動きが鈍い場合も寒さのサインかもしれません。一枚多く着せる、おくるみで包むなどして調整してあげましょう。
新生児がくしゃみを連発するのはなぜ?
くしゃみを連発する主な理由は、鼻の粘膜や鼻毛が未熟でとても敏感なためです。新生児は、わずかなほこりや温度変化、乾燥などの軽い刺激でも反応しやすくなっています。一時的なくしゃみであれば心配はいりません。
まとめ
- 新生児のくしゃみは反射や鼻粘膜の敏感さ、鼻毛の未発達など生理的な要因が主です。
- くしゃみ以外の症状がなければ多くは自然なもので、家庭での環境管理が基本対処です。
- 発熱や哺乳力の低下、呼吸困難など重篤症状が伴う場合は、すぐに医師へ相談しましょう。
- 風邪やアレルギー性鼻炎が疑われる場合も、同時に他の症状が出ていないか観察が大切です。
- 日頃から部屋の清潔・湿度管理を心がけつつ、不安な時は専門家を頼るようにしましょう。
release: 2025.09.18
- お気に入り機能はブラウザのcookieを使用しています。ご利用の際はcookieを有効にしてください。
また、iPhone、iPadのSafariにおいては「プライベートブラウズ」 機能をオフにしていただく必要があります - cookieをクリアすると、登録したお気に入りもクリアされます。