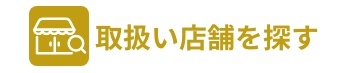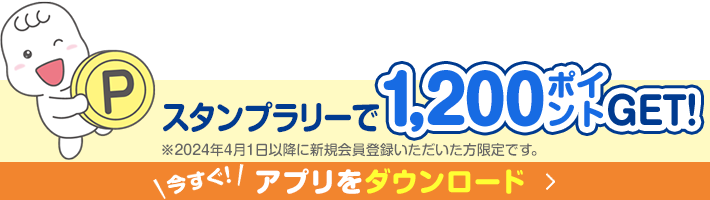妊娠初期の出血は大丈夫?無事に出産できる?原因を詳しく解説

妊娠すると多くの人が経験する、おなかの張り・痛み・出血…。今回は、とくに出血に注目! 妊娠初期の出血は、あまり心配しなくていいこともありますが、重大なトラブルのサインである可能性も。本当に注意するべき症状とは? 妊娠初期~中期~後期までの、出血について、その原因や、病院に行くべき症状の判断基準について、松田義雄先生に聞きました。
監修者プロフィール

松田義雄先生
代官山バースクリニック特別顧問、東京医療保健大学臨床教授
専門は周産期医学。鹿児島大学医学部卒業。鹿児島市立病院産婦人科、東北大学医学部附属病院麻酔科を経て、カナダ西オンタリオ大学医学部産婦人科・生理学教室留学。東京女子医科大学医学部産婦人科教授、母子総合医療センター母体・胎児科長。国際医療福祉大学病院産婦人科・周産期センター教授、JCHO三島総合病院院長を歴任。『CTGモニタリングテキスト』『早産のすべて』『脳性麻痺 周産期合併症/イベントとの関連』などの責任編集始め、単著、共著多数。エッセイ集『DAY BY DAY-I~Ⅳシリーズ』。
妊娠初期の出血はどのような感じ?
妊娠すると、「おなかが痛い」「つるように痛む」「おなかがぱんぱんに張る」というのは、みなさんよく経験することだと思います。でも、「出血」は、経験する人もいれば、しない人もいます。いずれも妊娠によって起こる症状で、おなかの赤ちゃんのことが心配になるのは、当然です。
とはいえ、ちょっとしたことを気にしすぎないでください。しばらく様子を見ていい状態、すぐに病院に行ったほうがいい症状などについて、お話しします。
妊娠初期(妊娠4~11週)の出血を経験する人は多い
妊娠初期出血は、妊娠初期に見られる出血のことで、妊婦の約2~3割が経験します。着床出血や内診後の出血など、心配の少ない原因で起こることもありますが、子宮外妊娠や早期流産など、要注意のものもあります。初期の出血はそれほど珍しいことではなく、その後問題なく妊娠が進み、出産にこぎつける人も多いです。でも、一方で、大事にいたることもあるので、注意が必要です。
妊娠初期(妊娠4~11週)の出血
妊娠初期(4~11週)に起こる出血の8割以上は、いわゆる着床出血といわれるもので、あまり心配ありません。しかし、自己診断は難しい。出血の量が多かったり、回数が多かったり、長く続いたりするなど、気になる場合は受診しましょう。
出血が続いても無事に出産できる?
妊娠初期の出血が少量で2~3日程度、と言う場合、多くは出産まで無事こぎつけることができます。ただし、流産の割合は、全体の約15%と言われています。この数字を多いとみるか、少ないとみるかは、人それぞれですが、仮に自分に起きた場合には、そのことで自分を責めてはいけません。初期流産の多くは、母体側ではなく、染色体異常など胎児側の問題であることが多いのです。むやみに落ち込まず、命の尊さ、不思議、奥深さを知る貴重な経験ととらえましょう。
出血があると、とかく不安になりがちです。心配な場合はかかりつけ医に相談しましょう。
着床出血ってどんな感じ?
生理と間違える?
妊娠初期に多い「着床出血」は、いったいなぜ、どうして起こるのでしょう? メカニズムを知っておきましょう。
卵子は卵管の膨大部で精子を待ち受け、受精すると、細胞分裂を繰り返し、成長しながら子宮へと移動します。子宮の内膜は、ホルモンの影響で厚くなり、受精卵を迎えるふかふかベッドのような状態になっています。そこに受精卵がたどりつくと、内膜に根を下ろし始めます。それが「着床」です。受精から着床するまでは、だいたい5~7日ほど。排卵日から数えると1週間後くらいです。
受精卵は着床すると、絨毛(じゅうもう)という組織を子宮内膜にのばし、胎盤をつくり始めます。そのとき、子宮内膜の血管を壊してしまうことがあるのです。それによって起こるのが「着床出血」です。着床出血が起こる期間は、着床から数日間で、それが生理開始予定日の頃に重なると生理と勘違いすることがあります。
その他の妊娠初期の出血の原因は?
初期の出血は、子宮外妊娠や流産、絨毛膜下血腫などが、原因のこともあります。出血の量などは、状況によってさまざまです。
子宮以外の卵管などに着床してしまう子宮外妊娠(異所性妊娠)では、体の外に出血しなくても、卵管の破裂などにより体内で大量出血して、命にかかわる重大な事態になることもあります。また、胎盤の元である絨毛膜と子宮(脱落膜)との間に血液が溜まる、絨毛膜下血腫が大きくなると流産や早産に移行することがあるので、要注意です。
いずれにしても、妊娠初期はまず正常な妊娠かどうかを医師に診断してもらうことが大切です。
【妊娠初期の出血の原因】
- 子宮外妊娠(異所性妊娠)
受精卵が卵管、卵巣、腹膜、頸管などに着床してしまう子宮外妊娠。胎児は子宮以外の場所で育つことができないので、いずれ破裂する。その時期が遅いほど、出血量が多く、母体も危険な状況にさらされるので、破裂する前に治療、手術をする必要がある。自然妊娠の場合1~2%、体外受精・顕微授精だと2~4%の割合で起こると言われる。
- 早期(初期)流産
早期(初期)流産とは、妊娠12週未満に起こる流産のこと。多くは、受精卵の染色体異常によるもので、治療は難しい。出血の量はケースバイケースだが、最初は潜血~暗赤色の少量の出血から始まり、子宮収縮による腹痛が起こることが多い。
- 絨毛膜下血腫(じゅうもうまくかけっしゅ)
胎児を包んでいる袋(胎嚢)の周りに血液が溜まったもの(血腫)ができる絨毛膜下血腫。出血量は、血腫の場所や状態により、少量から大量までさまざま。切迫流産・流産の原因の1つとされるが、妊娠の経過とともに、妊娠12週ころまでには出血なども落ち着いてきて、無事出産にこぎつけることも多い。
- 着床出血
受精卵が子宮内膜に着床して、絨毛の根を伸ばしているときに、組織や血管を傷つけて出血することがある。量は少なく、色は薄い赤やピンク、1日2日で治まることが多い。チクチクするような軽い痛みや不快感が伴うこともある。長引いたり、量が多い場合は、医師に相談する。
- 内診のあとの出血 など
腟内はたいへんデリケートな場所なので、内診の刺激によって出血することがある。妊娠中は全体に血液循環量が増えているので、出血しやすい。内診後の出血は、少量で1日2日で終わることが多いので、ナプキンを当てるなどして対処する。長引く場合は、医師に相談する。
【妊娠10週以降に初めて出血した場合の原因】
10週以降に初めて出血した場合は、次のような原因が考えられます。症状によって治療法は異なりますし、赤ちゃんや母体への影響も異なります。
- 子宮頸管ポリープ
子宮の入り口(頸部)の細胞が増殖してできた腫瘍で、ほとんどが良性。ちょっとした刺激で出血することがある。赤ちゃんに直接の影響はないが、子宮への感染症になる怖れがある場合、切除することもある。
- 子宮腟部びらん
子宮腟部が赤くただれているように見えるが、病的なものではなく、性成熟期の女性の8割に見られる。ちょっとした刺激で出血しやすい。ごくまれに、子宮頸がんの場合があるので注意が必要。
- 細菌性腟症
腟内の細菌のバランスが崩れ、乳酸菌が減少し悪玉菌が増殖した状態。症状は、不正出血やおりものの増加、生臭いにおい、下腹部痛など。無症状のこともあるが、子宮への感染などで流産につながることもある。
- 子宮頸管無力症
赤ちゃんの出口である子宮頸管が、出産にはまだ早い時期(妊娠14週~30週ごろ)に、緩んで開いてきてしまう。多くは無症状だが、不正出血やおりもの、腹部や腰の痛みがある場合もある。早産を予防するため、子宮頸管を縛る手術(子宮頸管縫縮術)を行うことがある。
- 内診のあとの出血 など
妊娠初期でも記載があるが、妊娠中期、後期も同様。腟内はたいへんデリケートな場所なので、内診したあとに出血することがある。出血は少量で1日2日で終わることが多い。
妊娠中の張りや痛みはなぜ起こる?
妊娠すると子宮はどんどん大きくなり、出産を迎えるまでの40週の間に、重さはなんと妊娠前の約20倍にもなります。子宮は筋肉でできているので、急激に膨らむと元に戻ろうとする力が働いて、それが張りや痛みとなって感じられるのです。
最初のうちは下腹部が痛み、子宮が大きくなるにつれて、だんだん上の方が痛むようになってきます。しかし、人によって子宮の位置が少しずつ違うので、痛くなる場所も微妙に違います。
子宮の下のほうを支えている子宮円索(しきゅうえんさく)という組織も引っ張られます。このため、足の付け根あたりが痛むことがあります。また、姿勢を変えたりしたときに背中の方まで痛みが走ることがあります。
便秘によって張りや痛みを感じることも
妊娠中はホルモンの作用で便秘になりやすく、その影響でおなかの張りや痛みが起こっていることもあります。
妊娠中にも多く分泌されているプロゲステロン(女性ホルモン)には、胃腸の働きを不安定にしたり、水分を保持しようとしたりする働きがあり、腸から水分を吸収するので、便秘になりやすいのです。
ホルモンの影響で妊娠中の体はダイナミックに変化
また、子宮筋腫を持っている人は、女性ホルモンの影響でさらに大きくなり、子宮に圧迫されて痛むことがあります。
筋腫は大きさや場所によっては、流産や早産、分娩障がいなどのリスクが高くなるので、超音波検査で筋腫があると診断された人は、経過を注意深く診ていく必要があります。
絨毛から分泌されるhCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン)というホルモンは、卵巣の中の黄体を刺激して女性ホルモンの分泌を促進しますが、ときに刺激し過ぎて、黄体に水分を溜めてしまいます。普段は2~3cmの卵巣に水が溜まって倍近くに膨れ、刺すように痛むことがあります(ルティン嚢胞/のうほう)。これも、妊娠8~16週目ぐらいになると、hCGの分泌が減ってきて、腫れも治まってくることが多いのです。
こうした妊娠中のダイナミックな変化が原因で起こる、おなかの張りや痛みは、自然なもの。おなかが張ったり、痛くなったりしたら、「休む、横になる」。1時間ほどで治まれば、あまり心配することはないでしょう。
妊娠時はおなか全体がかたくなる張り、出血にご用心!
張りや痛みで心配なのは、しばらく横になったり、座って安静にしても治まらないとき、出血があるときなどです。出血があるかないかは、とても重要です。
出血があったときには、子宮外妊娠、切迫流産や切迫早産、常位胎盤早期剥離(じょういたいばんそうきはくり)など、赤ちゃんやママの身に危険が迫っているサインであることも。少量でも出血があったら、医師に連絡して指示に従いましょう。多量の出血は、すぐに救急車を呼んでください。
妊娠中期(妊娠16週)以降の出血はすぐに受診!
何かおかしい…と感じたらすぐ病院へ!
妊娠中期(妊娠16週)に入ってからの出血は、たとえほんの微量の出血でも、すぐに診察を受けてください。この時期の出血は、切迫早産が圧倒的に多くなってくるからです。ポリープやびらんなど赤ちゃんに影響のないときもありますが、この時期の出血は、甘く見てはいけません。
近年、高齢出産が増えるにしたがって、切迫早産は増加する傾向にあります。とくに、初めて出血した、微量でも出血時におなかの強い張りを感じる、というときは、何はともあれ、かかりつけの医療機関に連絡を。激痛が起きた、大量に出血した、というときは、すぐに救急車を呼んでください。
【妊娠中期以降の出血の原因】
- 子宮頸管ポリープ
- 子宮腟部びらん
- 切迫早産(妊娠22週以降)
- 前置胎盤
- 常位胎盤早期剥離
- 内診のあとの出血 など
妊娠中期以降、注意するべき痛み
妊娠中期になってからのおなかの痛みで、注意して欲しいのは次のようなときです。おなかの張りや痛みがあって、体を横にしてしばらくして治まれば、ひとまずはだいじょうぶ。それでも痛みが続くときは、病院を受診してください。
【妊娠中期以降のおなかの痛み、受診の目安】
次のような痛みがあったときは、早産や全治胎盤、常位胎盤早期剥離など、重大なトラブルのおそれがあります。迷わず病院を受診してください。
- 繰り返し痛む、規則的に痛む。横になっても痛みが治まらない。
- 出血を伴った痛みがある。
- 痛みが治まらず、ずっと長く続く。
おなかの張り、痛み、出血の判断基準


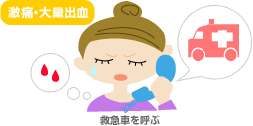
臨月の出血は病院に連絡
お産が近くなってからの微量出血の多くは、「お産に備える準備が整いましたよ」と体が知らせてくれる「おしるし」。赤ちゃんを包んでいる卵膜が子宮内膜からはがれ、その血液がおりものと混じったものです。
茶褐色やピンクのおりものがあると、数日から1週間くらいの間に陣痛が始まることが多いのです。おなかの張り、痛みがない場合は、ほぼ「おしるし」で心配ないものですが、一応、かかりつけの病院に連絡してください。
この時期、注意が必要なのは、おなかの張りや痛みを伴う出血です。もしも、おなかの張りや痛みといっしょに出血があったら、すぐに受診してください。
子宮出口付近に胎盤がある「前置胎盤」と診断されている人、分娩前に胎盤がはがれてしまう「常位胎盤早期剥離」などの場合は、緊急を要します。
常位胎盤早期剥離について
妊娠後期で出血が起こったら、特に注意したいのが、常位胎盤早期剥離です。
常位胎盤早期剥離は、赤ちゃんとママをつなぐ胎盤が、お産の前に子宮からはがれてしまうもの。そうなると、赤ちゃんに栄養や酸素が届かなくなり、赤ちゃんの命にかかわります。また、胎盤がはがれた部分から大量に出血するので、ママも危険な状態にさらされます。
※「常位」とは「胎盤が子宮の正常な位置についている」ということ。胎盤が子宮の出口にあってトラブルを起こしやすい前置胎盤ではない、という意味です。
「常位胎盤早期剥離」は、妊娠後期まで順調な経過だったのに、突然発症することがあります。もしも急に大量の出血をしたら、すぐに救急車を呼び、病院に行ってください。
●詳しく知りたい方はこちら
妊娠中の張り・痛み・出血の予防法は?
休みながら無理しないで過ごす
妊娠中のおなかの張りや痛みは、生理的なものでしかたないこともありますが、自分でも「今日はちょっと無理したかな」とか、「頑張りすぎた」「立ちっぱなしだった」というようなときに、起こることが多いのではないでしょうか。
妊娠したら、何をするにしても一気にしようとせずに、休み休みすることです。長時間同じ姿勢でいたり、立ちっぱなしでいたりするのは避けること。座ったり横になったりしながら、おなかや腰に圧がかからないように気をつけましょう。
腹圧をかけない生活を心がける
トイレでいきむのも、腹圧がかかるのでよくありません。ですから、便秘にならないようにすること。規則正しい生活、食生活も見直して、1日3食、野菜などもしっかりバランスよく食べましょう。せきやくしゃみも腹圧で子宮に刺激を与えます。風邪をひかないように、うがい・手洗い励行、人ごみにあまり出ていかないようにするなど、心がけてください。
内診のあとに出血することも
内診も子宮に刺激を与えるので、ときどき出血することがあります。健診のあとはできるだけ体を休めましょう。
横になって休んでも回復しないときは要注意
おなかが張っていると感じたら、横になって休みましょう。子宮への血流が増えるので、しばらくするとラクになるものです。それでも張りや痛みが続いたら受診しましょう。
胎動も気にかけてください
妊娠5ヶ月頃から、子宮の中の赤ちゃんが動くとママは胎動を感じるようになります。胎動はママと赤ちゃんのコミュニケーションツール。赤ちゃんの健康状態を知る、有力な情報源。医師にとっても、赤ちゃんの元気さを知るための、とても大事な情報です。
「いつもはもっと強く感じるのに、今日はなんだか胎動が弱い気がする」
「いつもは胎動を感じるのに、今日は感じないな。赤ちゃん、どうかしたのかな?」
そんなふうに感じたら、受診してください。受診して問題がなければ、ひと安心。でも万が一、赤ちゃんに何かあった場合には、できるだけ早い対処が重要になります。ためらわずに受診しましょう。
あまり心配しないで
妊娠中に不安やストレスが強いとストレスホルモンが分泌されて血圧が上がるなど、不調を招くことがあります。あまり心配やストレスを抱えないように、生活しましょう。
妊娠というのは、自分の中に自分とは別の存在である赤ちゃん(胎児)を受け入れている状態です。母胎であるママの体は徐々に変化して、出産の準備を整えていきます。ママの気持ちも最初は不安かもしれませんが、体の変化とともに胎動を感じたりすることで、やがて赤ちゃんを迎える期待感がふくらんでいくことでしょう。心配や不安で心をいっぱいにするのではなく、おおらかな気持ちで、その日を迎えてください。
おわりに
お母さん自身の健康が、赤ちゃんの健康に直結する、妊娠生活、育児生活。おなかの張りや痛み、出血は、まさに、“無理しないでね!”という赤ちゃんからのサイン。この声をしっかり受け止めて、無理せず、自分の体をいとおしんで、赤ちゃん誕生のその日を迎えてください。
はじめてのおむつ交換もあんしんの「おしりガイド」をご存じですか?

ムーニーは、赤ちゃんのおしりを置く場所がひと目で確認できる「おしりガイド」で、ママもパパも誰でも正しく簡単におむつ替えができます。
update : 2024.12.26
release : 2018.11.26
- お気に入り機能はブラウザのcookieを使用しています。ご利用の際はcookieを有効にしてください。
また、iPhone、iPadのSafariにおいては「プライベートブラウズ」 機能をオフにしていただく必要があります - cookieをクリアすると、登録したお気に入りもクリアされます。