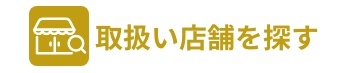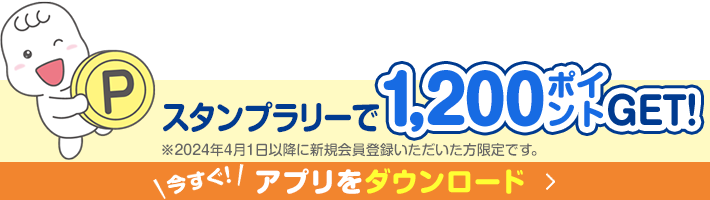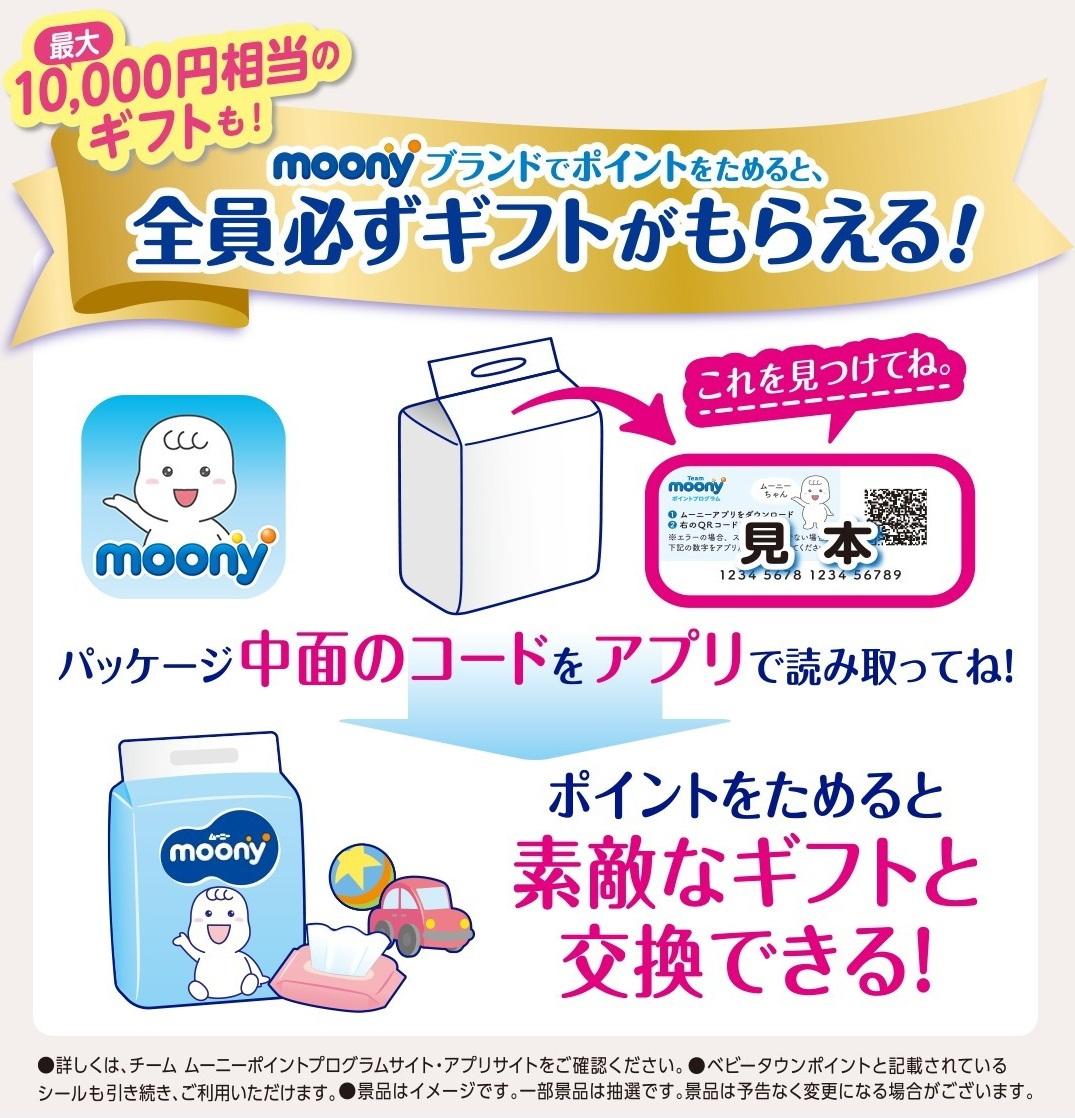【医師監修】新生児が便秘になったらどうする?うんちが出ない時の対処法や予防法、なりやすい時期を解説

「最後にうんちしたの、いつだっけ…?」とおむつを確認しては不安になる日々。特に新生児期は、赤ちゃんのちょっとした変化にも敏感になりますよね。うんちが出ない=便秘?と心配になる一方で、実はそれが正常なことも。この記事では、新生児の便秘の判断基準や原因、対処法、受診の目安について、育児中のママ・パパが安心できるようにご紹介します。
監修者プロフィール

今西洋介先生
一般社団法人チャイルドリテラシー協会代表理事
小児科医・新生児科医。日本小児科学会専門医/日本周産期・新生児医学会新生児専門医。医学博士(公衆衛生学)。一般社団法人チャイルドリテラシー協会代表理事。小児公衆衛生学者。富山大学医学部卒業後、都市部や地方のNICU(新生児集中治療室)で新生児医療に従事。「ふらいと先生」の名で、小児医療や育児に関する啓発を行い、社会問題解決に取り組む。現在は米国在住。3姉妹の父。 主な著書に『新生児科医・小児科医ふらいと先生の子育て「これってほんと?」答えます』(西東社、監修)、『小児科医「ふらいと先生」が教える みんなで守る子ども性被害』(集英社インターナショナル)ほか多数。
この記事で知ることができるのは?
- 赤ちゃんの便秘は、うんちの回数が週に3回未満、うんちが固い、うんちのとき赤ちゃんが泣いたり苦しそうにしていたりするなどの様子で判断できることを解説します。
- 新生児が便秘になる原因は、授乳量の不足、消化器官がまだ成熟していないなどいくつかの要素が絡んでいることを説明します。
- 消化器官が少しずつ発達する生後2~3ヶ月頃、離乳食が始まる生後5~6ヶ月頃になると便秘がちになる赤ちゃんが多いことを解説します。
- ディスケジア(乳児排便困難症)という、赤ちゃんが便をうまく出せない原因のひとつとなる症状について説明します。
- すぐに病院を受診した方がいい症状として、発熱があるか、お腹が張っているか、出血があるかなどの特徴を解説します。
- 赤ちゃんのうんちが出ない場合の対処法として、お腹や足、お尻のマッサージが有効であること、その方法がわかります。
- 赤ちゃんの便秘予防のために、生活リズムを整える、水分の摂取量を多めにするなど、家庭でできることを説明します。
新生児が便秘かどうか判断する基準
生まれたばかりの新生児でも、便秘になることがあります。心配なときは、以下の項目をチェックしてみましょう。当てはまる症状や様子がある場合は、便秘かもしれません。
- うんちの回数が週に3回未満
- 便がうまく出ない(排便困難)
- うんちをするとき、真っ赤になっていきむ
- うんちをするとき、泣いたりうなったりする
- うんちをすると肛門が切れる
- お腹がパンパンに張っている
- 母乳やミルクの摂取量が減っている
- 頻繁に吐く
- うんちが固くてコロコロしている
新生児が便秘になる原因
新生児が便秘になる原因としてまず考えられるのが、授乳量が足りていないことです。特に飲んだ量が見えない母乳の場合によくあるケースといわれています。そのほかの原因も含め、まとめました。
- 授乳の量が不足していて、うんちが作られない。
- 栄養分として吸収される量が多くうんちにならない。
- 生まれたばかりなのでうんちを出す行為に慣れていない。
- おむつかぶれなどの痛みを感じると我慢してしまう。
- 腸、肛門、神経などに先天的なトラブルや病気がある。
【時期別】新生児の便秘の特徴・原因
赤ちゃんは月齢によって、便秘の特徴や便秘になる理由が異なります。
- 新生児期…母乳不足により、便秘になることがあります。
- 生後2~3ヶ月頃…消化器官の発達により便秘になることがあります。
- 生後5~6ヶ月頃の離乳食を始めた頃…食事の変化が消化器官に影響し、便秘になることがあります。
1.新生児期
排便については1日に1~2回という赤ちゃんもいれば、1日に10回以上という赤ちゃんもいるなど個人差は大きいのですが、便秘はあまりみられない時期です。
便秘をした場合の主な原因は、授乳量の不足。体重が増えない、授乳をしてもすぐに欲しがる、おしっこの量が少ないなどの様子がみられる場合は、授乳量不足の可能性があります。特に母乳の場合は、飲んだ量を目で確認できないため必要量に達していないかもしれません。その場合はミルクを足して様子をみてみましょう。母乳とミルクでは、ミルクのほうがうんちが固めで回数も少なめになる傾向があるので、そのことも覚えておいてくださいね。
2.生後2~3ヶ月頃
生後2~3ヶ月頃になると、未熟だった赤ちゃんの消化器官も少しずつ発達します。栄養の吸収率がよくなり、ためておけなかったうんちもためておけるようになるでしょう。そのため、うんちの回数が減り、時には便秘となることもあります。
3.生後5~6ヶ月頃の離乳食を始めた頃
離乳食が始まる頃、赤ちゃんの腸はさらに発達します。便をためておけるようになり、うんちの回数もさらに減るでしょう。腹筋はまだ発達途上にあるためいきむ力が弱く、うんちが出にくくなることも。
また離乳食が始まると、摂取する水分量が減ります。そのため、うんちが固くなってしまい、便秘がちになる赤ちゃんも多いようです。
ディスケジア(乳児排便困難症)とは?
赤ちゃんが便をうまく出せない原因のひとつに「ディスケジア(乳児排便困難症)」という症状があります。
スムーズに排便をするためには、いきんだり肛門をゆるめたりという動作が必要です。排便のための協調運動といいますが、赤ちゃんはまだこの動きを上手に組み合わせることができません。そのため、便が固くなっているわけではないのに、うんちが出にくいことがあります。この状態を「ディスケジア(乳児排便困難症)」といいますが、厳密には便秘とは区別される症状です。
生後9ヶ月に満たない赤ちゃんによくみられる症状で、出た便がやわらかければ、治療をしなくても3~4週間程度で改善します。
すぐに病院を受診した方がいい症状
赤ちゃんが便秘かもしれないと気づいたとき、赤ちゃんの状態によってはすぐに医師の診察を受ける必要があります。便秘が続いている期間に関係なく、以下のような症状がある場合は迷わずに受診しましょう。病院に行くときは「うんちの回数や状態」「食欲やご機嫌はどうか」「授乳量や食事量」「最後のうんちが出たときの状況」「おならやげっぷは出ているか」についてメモをまとめて持参すると診察がスムーズです。
- ぐったりとして発熱している。
- お腹がかたくパンパンに張っている。
- 肛門が切れて出血がみられる。
- 授乳後や食後すぐに吐く、または嘔吐物が緑色をしている。
- 1週間以上、うんちが出ていない。
- いきんでもうんちが出ず、つらそうにしている。
- うんちをすることを嫌がって泣く。
新生児のうんちが出ない場合の対処法
赤ちゃんが「便秘かもしれない」と気づいたときには、家庭でできる対処法を試してみましょう。具体的には以下のような方法があります。
- お腹や足、お尻をマッサージする。
- 綿棒で浣腸する。
- 市販の便秘薬を使う。
マッサージ
赤ちゃんの便秘を解消するためには、マッサージも効果的です。おうちですぐに実行できますし、赤ちゃんとのスキンシップにもなります。マッサージをする部位は、お腹のほか、足やお尻もおすすめ。ママの手を使い、優しくなでたりさすったりすることで赤ちゃんの腸が刺激され、毎日取り組んでいると便通が整うことも期待できますよ。
お腹のマッサージ
安全な場所に、赤ちゃんを仰向けに寝かせて行いましょう。おへそのあたりに手のひらを当てたら、ひらがなの「の」の字を書くように、繰り返し優しくなでてあげます。「の」の字を書くのは、腸の動きに合わせるためです。服の上からでも裸でも、どちらでもかまいません。手や指先で圧迫するのではなく、そっとなでて腸を刺激することがポイントです。
足のマッサージ
足のマッサージも、お腹のマッサージと同じように赤ちゃんを仰向けに寝かせて行います。足元のほうから両方の足首を優しく握り、交互に屈伸させてください。赤ちゃんの太ももとひざがお腹に触れることで腸が刺激されます。マッサージというよりも、屈伸運動のお手伝いをするというイメージです。力を入れすぎたり、嫌がっているのに無理に動かしたりするのはやめましょう。
お尻のマッサージ
うんちが固くなって出にくいときは、赤ちゃんのお尻、肛門の上あたりを軽く押しながらマッサージすることも効果的です。赤ちゃんの顔が横向きになるような状態でうつぶせに寝かせて行いましょう。赤ちゃんの体はデリケートなので、少しの刺激にも敏感です。便秘を解消したいと思うあまり、強く押しすぎたりしないことを心がけましょう。
綿棒で浣腸する
マッサージをしてもなかなか改善しない、どうしてもうんちが出ないというときは、綿棒を使って浣腸するという方法もあります。方法は簡単です。清潔な綿棒を用意し、先端に、ベビーオイルかオリーブオイルを垂らしましょう。そのまま綿棒を赤ちゃんのお尻の穴に1~2cmほど挿し込み、綿棒を回しながら10秒ほど肛門を刺激してください。気を付けたいのは、挿し込みすぎたり強く刺激しすぎたりすること。綿棒浣腸は、あくまでも応急措置と考え、頻繁に行うことは避けてくださいね。
市販の便秘薬を使う
市販の便秘薬は、年齢によって使える薬が異なります。使う前に必ず医師に相談し、医師の指示のもと使うようにしましょう。そのうえで、対象年齢が明記された乳幼児向けの便秘薬を選びます。乳幼児が使える市販薬には、以下のようなものがあります。
- マルトース(麦芽糖)を主体としたもの
穏やかに腸を刺激して排便を促す薬です。甘くて飲みやすく効き目も穏やかなので、赤ちゃんにも使いやすいでしょう。 - 酸化マグネシウム
腸内で便を柔らかくし、排便を促す下剤です。刺激性がなく、使いやすいといわれています。 - 整腸剤
腸内の環境を整えることで便秘の改善を目指します。副作用も比較的少ないでしょう。
新生児の便秘を予防する方法
新生児や赤ちゃんの便秘を予防するための方法をご紹介します。
- 食事や睡眠などの生活のリズムを作る。
- 水分を意識して摂取する。
- 毎日の排便の記録をつける。
- 便秘によい食材を取り入れる。
生活のリズムを作る
授乳や離乳食はできるだけ同じ時間になるようにしましょう。時間を決めると、消化器官の働きにもリズムができてきます。できれば、夜の就寝時間も一定にするといいでしょう。睡眠には、排便のリズムをコントロールしている自律神経の働きを整える役割があります。生活のパターンが整うと、そのパターンにそって排便のパターンもできてくるはずです。
水分摂取を意識する
水分が少ないと、どうしても便が固くなってしまいます。特に離乳食をスタートした赤ちゃんは、それまでに比べると摂取する水分量が減るため、便秘になりがちです。栄養は食事からとりますが、減った水分も補えるように考えていきましょう。なお、新生児~生後6ヶ月は母乳/乳児用ミルクのみが原則です。WHOおよび厚労省ガイドでは「医療目的を除き母乳以外の飲食を与えない」と明記されています。
便秘によい食材を使う
便秘に効果のある食材の筆頭が、食物繊維を多く含む野菜や果物です。消化器官が未熟な赤ちゃんには、サツマイモやりんごなどがおすすめです。サツマイモなら、ペースト状にしたものをスープでのばすと食べやすくなります。りんごならすりおろせば、のどごしもよくなるので、積極的に使ってみてください。お腹の調子を整えるヨーグルトを取り入れることも方法です。
排便の記録をつける
毎日うんちが出る、2日に1回で元気に過ごしているなど、赤ちゃんにはそれぞれのリズムがあります。排便した時間、うんちの形や色などを記録しておくと、便秘かどうか、異常があるかどうかの目安になるでしょう。記録をしておくと、診察時にも状況をスムーズに伝えることができます。育児日記を書きがてら、うんちのことも記録してみてはいかがでしょうか。
先輩ママの体験談をご紹介します。
![]()
埼玉県:膝の上の黒すけ
もともとは授乳間隔を忘れないために始めました。良かったことは、授乳間隔を確認できることはもちろんのこと、生後1ヶ月を過ぎて便秘がちになった時に、うんちが何日間出ていないかの確認をすることもできたことです。上の子は卒乳した1歳ぐらいから育児記録をだんだんつけなくなっていきましたが、1歳までの記録があるのでたまに振り返ると、当時のことを思い出してとても懐かしい気持ちになります。今、下の子が生後4ヶ月なので、「上の子はこの頃こうだった」など、比較することもできるので便利です。
大阪府:かえるさん
トイトレを始めておしっこはすぐにできたけれど、うんちの時はカーテンの陰に隠れてしていました。便秘気味の子なので、なかなかうんちができなくて大変でした。気長に誘い、トイトレしました。トイレでうんちがうまくできたらシールを貼るようにしたら、ご褒美に釣られ、できるようになりました。
![]()
まとめ
- 新生児や赤ちゃんも便秘になります。
- 便秘の主な原因は、授乳量の不足、水分摂取量の不足、消化器官が発達していないことなどです。
- ぐったりして熱がある、吐く、苦しそうなどの様子がみられたら、すぐに受診しましょう。
- 市販の便秘薬を使うときは、事前に医師に相談し、対象年齢に合ったものを選び、使用法を守って使うことが大切です。
- 便秘解消には、家庭でのマッサージ、生活リズム作り、腹ばい運動も効果的です。
release : 2025.10.10
- お気に入り機能はブラウザのcookieを使用しています。ご利用の際はcookieを有効にしてください。
また、iPhone、iPadのSafariにおいては「プライベートブラウズ」 機能をオフにしていただく必要があります - cookieをクリアすると、登録したお気に入りもクリアされます。